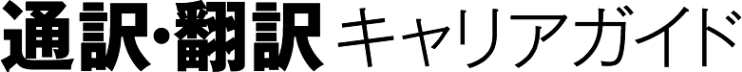Interview
未経験でも「翻訳センター」のトライアルに挑戦できる

「英語翻訳者養成コース」には「総合翻訳科」「ビジネス英訳科」「専門別翻訳科」があり、これから翻訳者を目指す人には、まず基礎力をつけることができる「総合翻訳科」がおすすめ。上級クラスに進むと、金融、マーケティング、IT、医薬などさまざまな分野についてまんべんなく学ぶため、自分の得意分野を見つけることができる。
「受講生はほとんどが社会人で、翻訳経験のまったくない方から社内で翻訳を経験している方まで、幅広いレベルにわたっています。すべての授業は双方向オンラインで実施しており、録画を視聴することができるため、欠席、遅刻等について心配する必要はありません」と、教務担当の横山正幸さん。
レギュラーコースは4月と9月に開講。受講開始前にレベルチェックテストを受け、「総合翻訳科」では、「基礎科1」「基礎科2」「本科」「実践実務科」の4レベルのうち、自分のレベルに合ったクラスに入る。「基礎科1、2」では原文の正確な理解と分析などについて学び、「本科」では訳文の品質向上を目指す。「『本科』の教材は実際に翻訳の現場で使われているものに近く、授業がすでに実践の場となっていると考えていただいていいでしょう」
「実践実務科」は全10回の授業の大半がOJT(On the Job Training)となり実務経験の機会を提供している。クラスの修了生は、グループ企業である「翻訳センター」のトライアルに挑戦することが可能だ。「『翻訳センター』のトライアル応募条件は、専門分野での実務経験または翻訳経験が3年以上となっていますが、本校の成績優秀者は、未経験でも応募することができます」。トライアルに合格すれば、「翻訳センター」の登録翻訳者として仕事を受注し、プロの道を歩み始めることになる。
授業は週に1回で、「基礎科1」から始めても、2年ほどでトライアルまで到達できる可能性がある。「現在は特に特許や医薬の翻訳者が不足しており、これからこういった分野で勉強を始める方には、大きなチャンスがあると言えます」
受講を検討している人に向けて、学習法や翻訳業界事情などに関する無料オンラインセミナーを3月と9月に開催している。さまざまな情報を手に入れて、着実にプロの道を目指そう。
講師インタビュー:効果的な学習法と訳文品質向上のコツ
(聞き手:担当教務 横山正幸さん)
横山さん 翻訳者を目指す人にとってはやはり、どういう学習法が効果的か気になるところですが、先生は普段どのように指導していますか?村瀬先生 翻訳とは単なる語句の置き換えではなく、書き手の伝えたいことをイメージとしてとらえ、読む人にも同じことをイメージしてもらえるよう、文章で表現しなければなりません。「読む」というインプットの練習は皆さんよく行っているようですが、「書く」というアウトプットのトレーニングが足りないようです。
私がよく勧めているのは、新聞記事などをそのまま書き写す「写経トレーニング」です。文章の構成方法を体得しつつ、覚えてから写した上で原本と比べることで、日本語では「てにをは」の使い方、英語では冠詞や前置詞の用法なども学べます。
横山さん 書き写すことで、内容をより深く理解することもできそうですね。
村瀬先生 特に英語の新聞や雑誌から書き写すことで、それぞれの語句が実際にどういう場面で使われているか、日本国内の出来事を英語ではどう表現しているかといったことも把握できます。
横山さん 訳文の品質を向上させるにはどうすればいいのでしょうか。プロとして仕事をする上では必須となりますが。
村瀬先生 和英辞典や類語辞典だけに頼らず、英英辞典を参照し、語義を立体的に把握する必要があります。例えばwithstandとendureはどちらにも「耐える」という意味がありますが、英英辞典を見ると、withstandには「極限状態に持ちこたえる」、endureには「我慢する」といったニュアンスがあるとわかり、そういった情報が正しい語彙選択に役立ちます。
横山さん 思い込みで訳してしまうと、誤訳につながりかねないのですね。
村瀬先生 現在、AIによる機械翻訳が増えていますが、AIは文を単独で訳すことはできても、文章全体を読んで筆者の意図をくみ取るというところまではいかない。そこはやはり、人間の翻訳者が担っていかなければならないと思います。
横山さん 翻訳業界では、常時翻訳者が不足している状態です。これからも多くの方々に、翻訳の仕事にチャレンジしてほしいですね。
※本インタビューは2024年時点の内容です。