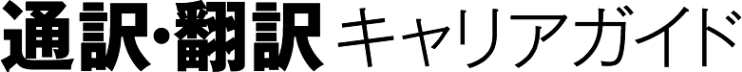Interview
環境分野の翻訳は、グローバル社会で活躍するチャンスを拡げる

国内最大手の翻訳会社が運営するサン・フレアアカデミーでは、医療やITなど専門性の高い分野の講座が充実している。その中でも2024年、注目なのが環境分野の社会的な課題をプロフェッショナルな視点から学べる講座だろう。
同校で環境分野の中級、上級、短期講座を担当している山崎厚子先生は、「SDGsの目標年である2030年が近づいていること、国際的な環境関連情報の開示に向けた要求のたかまりなどをうけて、各企業とも環境に配慮した自社の取り組みを発表する機会が増えています。国際的な基準・標準に則したCO2 排出量を報告する文書など、環境分野での翻訳はますます需要が高まってきています」という。
山崎先生は、大手シンクタンクでODAのプロジェクトをサポートし、さまざまな国の環境領域の資料をリサーチしてきた。その後、国際自然保護連合(IUCN)の日本での活動をサポートするなど、環境分野翻訳者のスペシャリストとしてキャリアを重ねてきた。
「環境分野の面白さは、扱うテーマの幅広さでしょうか。地球温暖化や大気汚染、生物多様性、再生可能エネルギーなど、あらゆる文書が扱えて、ショーケースのような体験ができるのです」
パワーポイントのスライド翻訳では、行間を読んで背景ごと意訳する
同じ環境課題についての文書でも、政府機関のオフィシャルなものから、少し柔らかめの民間団体の発信、あるいは経済活動の報告書など、それぞれのタイプに合わせた文体が求められる。
「授業のなかで、パワーポイントのスライドを翻訳してもらうことがあります。日本人がつくるスライドはたくさんの文字が並んでいることが往々にしてありますが、外国の方は、見出しと画像とキーワードのみというのが基本です。その行間を読んで意訳するのは、パワーポイント翻訳ならではのテクニックが必要になってきます。たとえば、GHGプロトコルやカーボンニュートラルなどの用語が出てきたら、それはどんな意味で、どの国の制度なのか、主体は誰なのかなど、周辺の知識を理解したうえで翻訳すると、訳文のクオリティが一層高くなります」
かつて、自動車のCO2排出について研究開発する技術者が、同講座を受講したことがあったそうだ。
「そのようなバックグラウンドを持つ受講者は、CO2排出量の技術面に特化して学びたいというご希望をお持ちだったので、そこを深掘りしました」
環境分野の翻訳講座を受講するレベルは、「中級編でTOEICのスコアが700~800ぐらいであればいいと思います。環境に関する背景知識などは、テキストに説明が細かく書いてあり、講座を受けながら学べますが、英語の文法書を確認したり、いろいろなツールを活用しながら文章を練り上げていったりすることを厭わない姿勢は必要ですね」
同講座の受講生は、企業の環境部門で働くビジネスマンもいれば、定年退職後に翻訳家をめざすシニア、主婦など、さまざまな世代が学んでいる。
「ざっくりと翻訳者になりたいと希望される方にとっては、環境分野と言っても、漠然としてイメージがわきにくいようです。範囲も広く、リサーチも必要なので、興味をもってもらう機会が少なかったかもしれません」と同社広報の石岡さん。
CSR・ESG情報を含む企業の統合報告書の翻訳には環境分野の知識が必須
それでも、SDGsに関するメディア報道などから、世間の環境への関心が高まり、特にグローバルな事業展開を行っている企業をはじめ、環境意識の高い企業は統合報告書を作成することを選択し、自社のCSR (企業の社会的責任)やESG (Environment環境・Social社会・Governanceガバナンス)を公表し始めている。
山崎先生は環境分野の翻訳に興味をもつ方々に、こんなメッセージを伝える。
「環境への取り組みは、企業にとってミッションなので、今後こうした環境分野の文書翻訳の需要はますます高まっていくでしょう。環境分野のトピックや関心事項、環境を巡る議論は、人間社会の変化に伴って変化していきます。したがって、環境分野の翻訳者は、翻訳を続けていく限り、新しい知識を吸収していくことが求められます。この新たな知識を獲得するプロセスの楽しさを発見しながら、学習を進めてもらいたいと思います」
サスティナブルな社会を実現するために、あなたにできることがあるかもしれない。
※本インタビューは2024年時点の内容です。