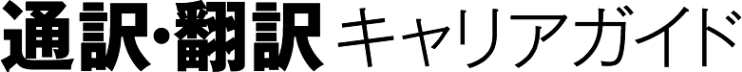関口涼子さん
フランス・パリを拠点に翻訳家として活躍している関口涼子さん。詩人、作家としても数々の作品を発表し、食や味覚に関する創作活動も展開。2012年にはこれまでの功績が認められ、フランス政府から芸術文化勲章シュヴァリエを授与された。国境を超えて多彩な才能を開花させた関口さんの歩みは、「言葉」との対話を続けてきた歴史でもあるという。
「言葉」という他者との脆くも楽しい関係

1970年東京都生まれ。パリを拠点に翻訳家、詩人、作家として活躍。2012年にはフランス政府から芸術文化勲章シュヴァリエを授与される。訳書に、M・エナール『話してあげて、戦や王さま、象の話を』(河出書房新社)、A・ラヒーミー『悲しみを聴く石』(白水社)、P・シャモワゾー『素晴らしきソリボ』(河出書房新社)など。日本文学やマンガ作品の仏語訳も数多く手掛けている。
高校時代に知った人に伝えることの喜び
「子どもの頃から読書が好きで、『クマのプーさん』『メリー・ポピンズ』といった海外文学の翻訳本もたくさん読んでいました。子どもながらに、自分の暮らしている国とは異なる世界があることも、理解していたように思います」
また、子どもの頃に「言葉」というものを強く意識したあるエピソードを教えてくれた。
「テレビドラマにもなった『大草原の高校時代に知った人に伝えることの喜び小さな家』というアメリカの小説シリーズをいつも楽しみに読んでいたのですが、あるとき、続編が違う出版社から出ることになり、それにともなって翻訳者も交替。それまで主人公家族の子どもたちは、両親を〝父さん、母さん〟と呼んでいたのに、突然“父ちゃん、母ちゃん”と呼ぶようになったのです。その違和感が最後まで拭えず、言葉ひとつで伝わり方が大きく変わってしまうということを認識するきっかけにもなりました」
高校生になると、詩人である朝吹亮二氏などの影響で詩を詠みはじめ、『現代詩手帖』(思潮社)へ作品を投稿。17歳の若さで「現代詩手帖新人賞」を受賞する。
「賞もうれしかったのですが、それ以上に雑誌を通して、私の詩をたくさんの人に読んでもらえたことがうれしかった。言葉を介して、人に何かを伝えることができる喜びは、昔も今も変わりませんね」
渡仏で気付かされた母国語との関係性
フランス語での著作も10冊を超える関口さん。しかし、フランス語を学びはじめたのは、意外にも大学に入ってからだったという。「フランス語を選んだのは、フランス文学に興味があったのと、料理の美味しそうなイメージに惹かれて(笑)。英語があまり得意ではなかったので、フランス語は落ちこぼれまいと、大学の授業だけでなく、神楽坂の東京日仏学院(現アンスティチュ・フランセ東京)にも通って勉強しました」
大学在学中にフランスのナンシーという町に留学。フランス語上達のため、あえて日本人のいない小さな町を選んだ。しかし、日本語から隔離されたことで、逆に日本語との距離感を意識することに。
「当時はインターネットもなく、国際電話の通話料も法外だったので、半年以上日本語に触れませんでした。その間、フランス語は上達したものの、日本語が自分からどんどん遠く離れていくことに気付いたのです。もちろん話せなくなるほど忘れることはありませんが、母国語ですらアイデンティティーの一部ではないという驚き。そこで初めて、外国語と同様に、日本語も自分とは別の〝他者〟であることを知ったのです」
その経験から、現在はフランス語より日本語の本を多く読むように意識していると語る。
「海外で生活していると日本語を忘れていく危機感が常にあります。今はインターネットでいつでも日本語の記事が読めるし、日本の本も手軽に入手できるので、ありがたい時代になりましたね」
その後、大学院の博士課程で再び渡仏。そこでフランス現代詩に触れ、大きな刺激を受ける。
「性別や国境にとらわれず、自由に表現している作風が魅力的でした。文学や芸術の面でいうとフランスはすごく懐が広い。私の中でも、この国で自分の作品を発表したいと想いが募っていきました」
そして、彼女は思い切った行動に出る。自分の詩集を自らフランス語に翻訳し、パリのある出版社に送ったのだ。
「一人の表現者として作品を見てほしかったので、自分の言葉をフランス語にする必要がありました。その想いが通じたのか、半年後に出版社から連絡が来て、まさかの出版化が決まったんです。本当に信じられない気持ちでしたね」
この一件がひとつのきっかけとなり、日本で研究者となる道ではなく、フランスに残って翻訳者兼作家となる道を選択。それは「言葉」という他者との対話を続けていく覚悟であったのかもしれない。


文学作品だけでなくマンガの翻訳にも注力
フランスに残って本格的に活動を始めた関口さん。当初は文学作品の翻訳より、マンガを翻訳する仕事が多かったという。
「ちょうどフランスで日本のマンガ人気に火がついた頃であり、タイミングに恵まれました。もともとマンガも大好きでしたし、日本の素晴らしいマンガ作品を外国に紹介するお手伝いができるのはとても有意義なこと。学生時代から愛読していた岡崎京子さんや萩尾望都さんの作品もフランス語に翻訳することができて、本当に光栄でしたね」
文学作品の翻訳者がマンガを翻訳することは珍しい。なぜならマンガ翻訳は、文学作品の翻訳に比べて少し軽く見られている風潮があるからだ。しかし、両方の翻訳をこなす彼女の見解は異なる。
「マンガ作品にはそれぞれ独創的な世界観があり、セリフの言葉も面白い。マンガにはマンガの魅力があり、文学より劣っているとは思いません。私にとってはマンガ翻訳もとても大切な仕事です」
一方で、関口さんはフランス文学を日本に紹介する役割も担っている。パトリック・オノレ氏との共同作業で翻訳した『素晴らしきソリボ』(河出書房新社)は、第2回「日本翻訳大賞」に輝いた。
「日本語への翻訳をフランス人との共同作業で手掛けたのは初めてでしたが、いろいろ勉強になりました。作品の世界観が難解な場合は、他者からの意見で気付くことが多いし、自分と違った解釈を知ることもできます。翻訳や執筆は一人で行う作業と認識されがちですが、自分の思考だって本の言葉や他者との会話などに影響を受けている訳ですから、複数で対話しながら進めてもいいんですよ。その分、稼ぎは減りますけど(笑)」
フランスで暮らす日本人翻訳家として
関口さんの意識の中では、フランスから日本を眺めるとともに、日本人としてフランスを見ている部分もあるという。だからこそ両国のズレに対して敏感に反応する。2015年1月、テロリストに襲撃された『シャルリー・エブド』誌は、事件後最初に発行した号で、イスラム人男性と思われる風刺画に、「Tout est pardonné」との見出しをつけた。日本のメディアは、これを「全て許される」と訳し、そこには表現の自由に対する訴えも含まれていると解釈した。しかし、本来は「全てを赦した」という意味であり、襲撃事件も含めた過去を全て受け止め、前に進もうというメッセージだったのだ。関口さんは日本の新聞社にこの誤訳を伝え、書籍やウェブメディアに正しい見解を綴って寄稿した。
「フランスにおける3・11の報道についても偏りを感じ、フランス語で福島原発のクロニクルを発表しました。これからも何か気付いた部分があれば、できる範囲で伝えてきたいと考えています」
関口さんにとって、翻訳家という仕事の魅力はどこにあるのか。
「私は言葉マニアなので、言葉という他者と向き合う作業が楽しい。それは恋愛で少しずつ相手のことを理解する過程にも似ている。言葉は不完全なものであり、決して万能ではありません。例えば、味覚に関して〝渋い〟という表現はフランス語に存在しない。そこをどうやって補い、表現するのか。言葉は完璧じゃないから面白い。それがつらいと感じる人は、翻訳者に向いてないと思いますね」
今後について尋ねると、やりたいことがありすぎて時間が足りないと笑う関口さん。これからも、日本語とフランス語という「二つの他者」との対話は続いていく。
取材・文/谷口洋一
この記事は「通訳・翻訳キャリアガイド2017」に掲載されたものです。