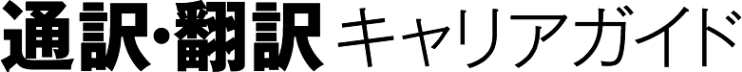越前敏弥さん
世界的なベストセラーシリーズの翻訳をはじめ、著書の出版や読書会への参加など、幅広く活躍する越前敏弥さん。翻訳者として確固たるキャリアを築きつつ、多岐にわたる活動を積極的に行う原動力はいったい何なのだろうか。
文芸翻訳者に不可欠なのは「本が好き」という想い

人脈や仕事を得るには工夫と努力が必要
大ベストセラー『ダ・ヴィンチ・コード』(ダン・ブラウン著)の翻訳や、エラリー・クイーンの新訳などを手掛ける越前敏弥さん。翻訳者を志したのは30代前半、大病を患ったことがきっかけだった。
「学生時代は映画が好きで、自主映画を撮っていました。その費用を稼ぐため、学習塾の講師や留学予備校のカウンセラーをしていたのですが、いつしかそちらの方が忙しくなり、生活の中心に……。働きづめだった32歳のとき、くも膜下出血で倒れて入院。死に直面し、この世に何か作品を残したいと思うようになりました」」
これを機に、「自分にできることは何か」と考え、本が好きだったこと、そして仕事で長年、英語に接していたことから、現実的な選択として文芸翻訳の道へ。翻訳学校に3年半通い、恩師である田村義進さんの紹介で在学中から仕事を開始。卒業と同時に、初の長編の翻訳本が出版された。
以来、多彩な翻訳作品を手掛けているが、転機となったのは『飛蝗(ばった)の農場』(ジェレミー・ドロンフィールド著)。出版当初はあまり売れ行きが伸びなかったが、『このミステリーがすごい!2003年版』(宝島社)の海外編・第1位に選ばれたことで売れ始め、越前さんの名が知られることとなった。
そもそも本作の翻訳を依頼された発端は、越前さんが別の作品を出版社に持ち込んだこと。そのとき編集者に「〝時空を飛び交う〟という似たような内容で、もっとおもしろい小説がある」と『飛蝗の農場』を紹介され、内容に強く惹かれて依頼を受けた。つまり、自身の持ち込みが間接的に役に立ち、仕事が舞い込んだわけだ。
『飛蝗の農場』には自動車に関する記述が随所に登場するが、越前さんは当時、車の免許を持っておらず、内容を理解するのが困難だった。そこで、40歳にして初めて自動車教習所へ。自腹を切ってまで免許を取ったことで小説の内容をイメージしやすくなり、翻訳を進めることができたという。
こうして完成した『飛蝗の農場』の出版日、新たに依頼されたのが『天使と悪魔』(ダン・ブラウン著)の翻訳だ。
「翻訳者や編集者、書評家が200~300人集まる忘年会で、僕は幹事と司会を担当。司会を終えてステージを降りたとき、角川の編集者から『今後、何かあれば翻訳をお願いしたい』とあいさつされて。数カ月後、実際に『天使と悪魔』のお話をいただきました」
多くの業界人が集う場で、単に名刺交換をするだけでは覚えてさえもらえない。方法は人それぞれだが、人脈を築くには、それ相応の努力が必要だと越前さんは言う。
「フリーランスの翻訳者には、人付き合いが苦手な人も多いのですが、フリーランスこそ人付き合いが大事。僕もパーティーは好きではありませんが、若手の頃は、できるだけ参加するようにしましたし、司会も務めました」
こうした人脈づくりに加え、何より重要なのは仕事で目立つこと。当時、越前さんは締め切りまで2、3週間ある仕事を3日で仕上げていたという。
「できあがったものを編集者に早く提出して、『おかわりください』と(笑)。もちろん早いだけでなく、中身が伴うことが大前提ですが、そうした積み重ねで信頼を得ることが、次の仕事につながっていくと思います」

翻訳作業の基本は読者を第一に考えること
翻訳の仕事をするうえで越前さんが心掛けているのは、作品の素晴らしさを台無しにしないこと。翻訳書が売れるかどうか、その1、2割の責任は翻訳者にあると考え、仕事をしている
さらに、越前さんが意識しているのは優先順位を明確にすること。文芸翻訳で優先すべきは、読者、原作者、出版社の三者。基本的には全員に尽くしたいが、一者を選ばなければならないときは、①読者→②原作者→③出版社の順で優先。「読者=お客様」のことを一番に考えるのは、どんな仕事も同じだ。翻訳において読者を優先する典型的な例が、訳注の入れ方だという。
「例外はありますが、一般的に訳注が入り過ぎると文章のリズムが悪くなるので、原作者と翻訳者は入れたくない。一方、出版社は内容をわかりやすくするため、できるだけ入れたがる傾向がある。そんなときは読者を優先し、訳注がないと読者がまったく理解できそうにない場面や、物語の展開上、訳注がないとミステリーとして成立しない場合にだけ入れることにしています」
着実にキャリアを積み上げてきた越前さん。文芸翻訳者に不可欠なのは「本が好き」という想いだと語る。
「よく『英語が好きで仕事に生かしたい』と翻訳者を目指す人がいますが、英語はあくまでも仕事の道具。文芸翻訳だったら本、映像翻訳だったら映画、産業翻訳だったら担当する業界・分野に興味がないと長続きしません」
とはいえ、現実に依頼があるのは、必ずしも好きなジャンルの仕事とは限らない。現在はロマンス小説やノンフィクションの翻訳が増えているが、それでも興味が持てるかどうかは重要。依頼を受けるまでは興味がなくても、翻訳を始めてみたら、おもしろくてどんどん読むようになったという翻訳者も多い。要は翻訳を「楽しい」と感じられるかどうかがポイントなのだ。
「たとえば、ひとつの訳語を決めるのに、数カ月を要することがあります。ダン・ブラウンの最新作『オリジン』では、ひとつの訳語を決めるのに2カ月かかりました。そうした作業を楽しいと思える人じゃないと長続きしない。楽しみながら、辞書を片手に多様なタイプの文章と格闘することで、表現力も培われていきます」
そしてもうひとつ、文芸翻訳者に必要なのは「調べものが好き」ということ。前述したように、越前さんは自動車の仕組みを理解するため、文献に当たるだけでなく実際に自動車学校に通った。さらに、ダン・ブラウンの『ロスト・シンボル』を翻訳した際は、物語に登場する「フリーメイソン」東京ロッジ(本部)に赴き、インタビューを実行。こうした探求心が、素晴らしい翻訳を生む源といえよう。
翻訳書の読者を増やすべく各地で読書会に参加
越前さんの仕事のモチベーションとなっているのは、第一に本が売れること、そして次に読者からの声。現在は出版業界全体が縮小傾向にあり、翻訳書も読む人が減っている。しかし越前さんは、翻訳書を愛しているからこそ、「売れない」とただ嘆くのではなく、読者を増やしていくため、自らが前向きに翻訳書の素晴らしさを発信していくべきだと考えている。その活動のひとつが読書会。2カ月に一度は、日本各地の読書会に参加している。
「読書会は翻訳書の魅力を知ってもらうのと同時に、読者の生の声を聞ける場。最近は美術作品をテーマにしたり、各地のラーメンを紹介したりと、さまざまな人を巻き込む試みを行っています。今後も各地で積極的にイベントを企画し、たくさんの人に翻訳書の愉しみを知っていただきたいですね」
取材・文/籔 智子 写真/三浦義昭
この記事は「通訳・翻訳キャリアガイド2019」に掲載されたものです。