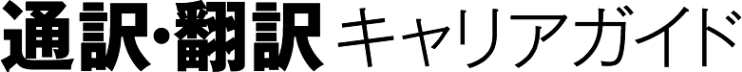【連載コラム 第32回】
越前先生の「この英語、訳せない!」
ビシッと決まる訳語の裏には翻訳家の人知れぬ苦労があります。
名翻訳家の仕事と思考のプロセスを追体験できる、珠玉の翻訳エッセイ。
度量衡で示す訳者の考え
文化的背景のちがいが原因で翻訳がむずかしくなる例として、まず思いつくのは度量衡の問題です。おもに英米で用いられているfoot(feet)やinch、あるいはpoundやounceなどの単位は、日本で使われているメートルやセンチ、キロやグラムなどに変換すべきなのでしょうか。
翻訳の仕事の現場に長くいる立場から言うと、わたしがこの仕事をはじめた20世紀末ごろには、まちがいなく英米の単位をそのまま残すほうが主流でしたが、いまは日本で使われている単位に直す人のほうが多くなっています。ただ、これも経験上言えることですが、そのまま残せばわかりにくいと批判する人がかならずいて、変更すれば英米人がメートルやグラムを使うかに見える不自然さを批判する人がかならずいます。どちらにせよ文句を言われるなら、自分が正しいと信じる道を貫くべきなのでしょう。最近のわたしは、古典作品や格調高い作品では原語の単位をそのまま残し、現代的なエンタテインメントでは日本人のわかりやすい単位に変える、という方針で仕事に臨んでいます。
そのまま残して訳す場合に注意すべきなのは、たとえば身長が6feet 7 inches(約2メートル)の人が出てきたら、前後関係から必要な場合は「長身」などの最小限の情報を補うことでしょう。一方、日本式の単位に変える場合は、たとえばexactly 5 feetなら、それを忠実に「ぴったり152.4センチ」などとするのは通常は無意味で、文脈しだいで「ぴったり150センチ」にするのか「150センチ余り」などとするのか、日本語のなかで自然な言い方を選ぶべきだということです。
また、温度はFahrenheit(華氏)のままではあまりにもわかりにくいので摂氏に変えるのがふつうですが、一方、翻訳フィクションでdollarを日本円に換算してあったら奇妙に感じる人がほとんどでしょう。これらを両極端として、長さや重さなどの単位はそのあいだに位置づけられ、どちら側を選ぶかは最終的に訳者の裁量で決まります。
もうひとつ注意してもらいたいのは、同じ単位でも国や場面によって意味が異なる場合です。たとえば、tonという単位は、日本では「1トン=1,000キロ」とだれもが覚えていますが、アメリカなどでは1トンが2,000ポンド(900キロ余り)、イギリスなどでは2,240ポンド(1,015キロ程度)と見なされることが多く、1,000キロに相当するのは1 metric tonです。また、mileも海上や空では別の意味で使われることがあり、訳語を選ぶときは、どの意味で使われているのかや何を伝えるべきなのかを考える必要があります。

越前敏弥(えちぜん としや): :文芸翻訳者。1961年、石川県金沢市生まれ。東京大学文学部国文科卒。訳書『オリジン』『ダ・ヴィンチ・コード』『Yの悲劇』(KADOKAWA)、など多数。著書に『この英語、訳せない!』『「英語が読める」の9割は誤読』(ジャパンタイムズ出版)、『日本人なら必ず誤訳する英文・決定版』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。