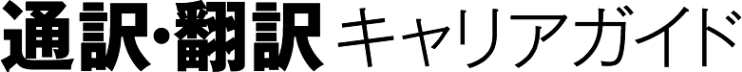【連載コラム 第2回】
越前先生の「この英語、訳せない!」
ビシッと決まる訳語の裏には翻訳家の人知れぬ苦労があります。
名翻訳家の仕事と思考のプロセスを追体験できる、珠玉の翻訳エッセイ。
いつも悩ましいsorry 問題

翻訳者ならだれでも訳出に苦しんだ経験があるのが、このsorry。いつも「ごめんなさい」と訳せるわけではありません。
記憶に新しいところでは、テニスの大坂なおみ選手が2018年の全米オープンで初優勝したとき、決勝の相手のセリーナ・ウィリアムズ選手が審判と揉めたことなどを受け、インタビューで“I’m sorry it had to end like this.”と言ったことが話題になりました。大坂選手は「ごめんなさい」と謝ったのか、「残念です」と言っただけなのか、どちらだったのでしょうか。実のところ、これはどちらか一方が正訳だと決められるものではなく、つねに両方のニュアンスが含まれているわけで、翻訳者は前後関係や間合い、雰囲気や表情などに注意して総合的に判断するしかありません。わたし自身は、どちらかと言うと「残念です」に近い印象を受けましたが、のちに大坂選手自身がこの発言を評して“I felt like I had to apologize.”と言ったらしいので、謝罪の含みも少しあったのでしょう。
わたしの訳書『おやすみの歌が消えて』(リアノン・ネイヴィン、集英社)では、主人公ザック(6歳の男の子)のお兄さんが小学校での無差別銃撃事件で命を落とし、息子の死を知ったお父さんがお母さんに対して“I’m sorry, babe, I’m so so sorry!”と告げる一節があります。同情を表しているのですから、ふつうなら「残念だ」や、場合によっては「気の毒に」と訳すところですが、ここはザックが兄の死を理解できず、なんらかの理由でお父さんがお母さんに謝っていると勘ちがいする場面でもあるので「すまない」「本当にすまない」と訳しました。ぴったり合うわけではありませんが、苦肉の策としてそうしたわけです。小説などではsorryについて、このような誤解に基づくやりとりが描かれる場合が少なくありません。
ダン・ブラウンの『インフェルノ』(角川文庫)では、記憶喪失に陥った主人公ラングドン教授が、以前自分が言ったことばの録音音声を耳にしたとき、それが“Ve … sorry.”と聞こえます。当然「ヴェリー……ソーリー」だろう、さて自分は何を謝っているのだろうかと迷い、それが作中の大きな謎のひとつとなって、読者を惹きつけます。ミステリー小説なので、答は明かせませんが、少しだけヒントを出すと……16世紀の美術史に関係があります。ぜひ読んでみてください。
* 本コラムは『この英語、訳せない!』(ジャパンタイムズ出版刊)から抜粋して掲載しています。