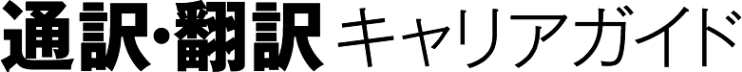【連載コラム 第23回】辛酸なめ子の英語寄り道、回り道
田村かのこさんに聞く「アートトランスレーター」
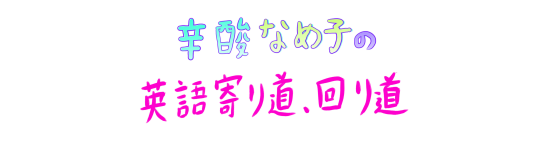
美術の展示でたまに見かける通訳の女性の有能ぶりが印象に残っていました。来日した現代美術家の、抽象的で感覚的な表現を当意即妙に訳される知識や語彙、センスなどに感じ入り、いつか話を伺ってみたいと思っていました。 ポーラ美術館でのフィリップ・パレーノ展でフィリップ・パレーノ氏の通訳をされていたときは会場が混み合っていてチャンスがなく、エスパス ルイ・ヴィトン大阪で24年11月から始まったドイツ人アーティスト、ウラ・フォン・ブランデンブルク氏の展示会場でついに話しかけることができ、今回の取材につながりました。ウラ・フォン・ブランデンブルク氏は精神世界などをモチーフにしていて、通訳も難しそうでしたが、アーティストと立ち話したときの妖怪談義も訳していただいて、ひとときの交流を持つことができました。
今回は、その時通訳されていた、アートトランスレーター(アートを専門としている翻訳・通訳者)、田村かのこさんにお話を伺います。インタビューの場所は、港区の旧三田図書館内の「みなとコモンズ」。田村さんが「コモニング・ファシリテーター」をつとめられる、港区の新たな居場所づくりの取り組みの場です。港区はハイソで近寄りがたい印象でしたが、「みなとコモンズ」は砂浜に見立てたスペースがあったり、無料の飲み物があったりでかなり居心地が良いです。
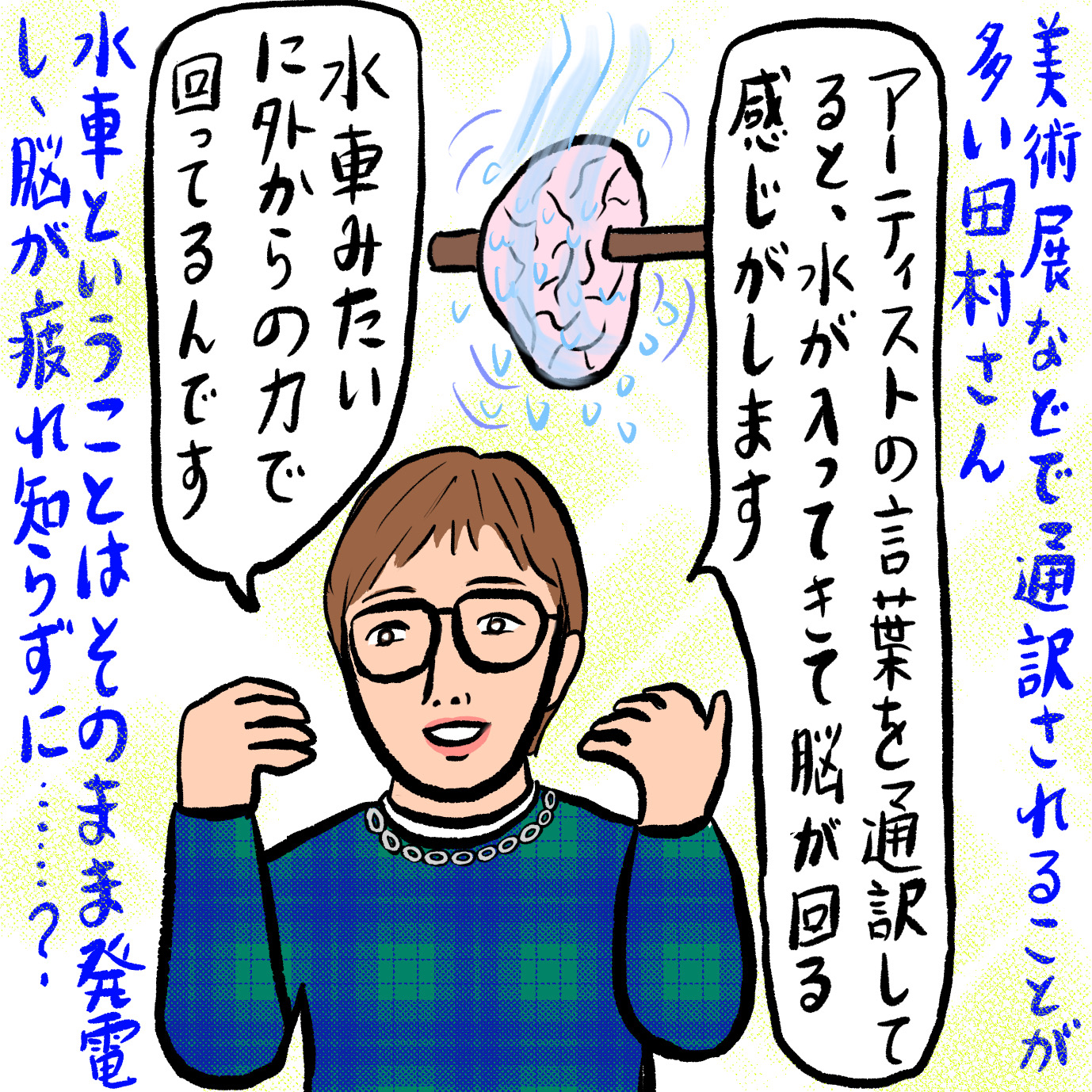
「9月末にオープンして3月までこの場は継続される予定です。砂浜は、必ずしも皆で手を取り合って仲良くするのではなく、お互いが、あ、いるな、というくらいの距離感で居心地よくいられる空間をイメージしています。ここでは朗読をしてもいいし寝てもいいし、赤ちゃんが来てもいい。茶話会やハンドマッサージなども行なわれています。翻訳は言語から言語の通訳とは限らないので、この場所は大きな意味での翻訳の仕事だと思っています」
田村さんの雰囲気とも合っている素敵な空間です。アート専門の翻訳・通訳者の活動団体「Art Translators Collective」の代表とのことですが、どういった団体なのでしょう。
「参加者は12人くらいで、会社組織じゃなくてアーティストのユニットみたいなイメージ。アートに関する翻訳や通訳をやっている人たちが、お互い助け合いながら主体的に活動していく、という団体です。仕事の依頼が来たら日程と条件や内容を見て誰がやろうか話し合っています。複数人必要なプロジェクトもあります。フリーランスで翻訳・通訳していると孤独な戦いが多くて、相談できる仲間がいると助かります」
たしかに、確定申告の時期とか相談相手がほしくなる気持ちはわかります。お互い仕事を取り合うのではなく、得意分野を生かして誰が引き受けるか決められるのは平和で理想的です。急に体調が悪くなったときにも誰かに頼めて、発注側にとっても安心感が。
ところで田村さんの語学力とセンスはどこで培われたのでしょうか。
「高校時代から留学していました。スイスのアメリカンスクールに3年間に通い、アメリカの大学に行って、アメリカの大学在学中の1年間はイギリスに交換留学に行きました。通算、スイスに3年、アメリカ3年、イギリス1年で7年間海外で学びました。親が、私をアメリカの大学に行かせたい、というのがあって、大学からだと大変だから高校から英語圏に通わせたいと思ったようです。イギリスとスイスどっちがいいか聞かれて、島国じゃないスイスを選びました」
そんな選択肢、自分の家では一切提示されなかったです。スイスの私立校というと、超富裕層や各国の王侯貴族が集まっているイメージで憧れますが……。
「中にはそういう人もいたと思いますが、50カ国くらいからいろんな人たちが来ていましたね。全校400人いかないくらいの小さい学校でした。制服はなかったですが、かわりにドレスコードはありました。ジーンズやTシャツは禁止で、女の子はブラウス、男の子はブレザーにネクタイで、靴は革靴みたいな」
校則じゃなくてドレスコードというのははじめて聞きました。10代の頃からどこでも通用できる気品やマナーが身につけられそうな学校です。
ちなみに田村さんはスイスははじめてではなかったそうです。
「一応、中学の段階で準備のため、スイスのサマースクールやイギリスの語学学校に通いました」とのことで、ヨーロッパ慣れしています。そして学費もすごいことになっていそうです。
「両親は自分たちは語学で苦労したので娘には早い段階で……と思っていたようです。スイスの物価は、今の方が全然高いですね。当時も安くはなかったですけど」
スイスの高校はプロムはあるのでしょうか。
「ありましたよ。アメリカのティーン映画に描かれるほどクレイジーではなかったですが、ドレスアップして男子学生にエスコートしてもらって参加しました」
スイスの高校で過ごし、プロムも体験。普通ならこれで満足して帰国しそうですが、田村さんはアメリカのタフツ大学に進学。選んだのは土木工学部というのが意外です。
「もともと絵を描くのが好きだったんですが美大に行くイメージがあまりなくて、一般教養の大学に進学することにしました。ヨーロッパで教会など素晴らしい建築をたくさん見る機会があり、建築にも興味がわいて、数学も好きだったのでタフツ大の建築系の学科ということで土木工学部を選びました」
建築の構造計算などもできるそうですが、さらにすごいのは日本に帰国してから美術予備校に入り、今度は東京藝大を受験して約半年の受験勉強で先端芸術表現科に合格。多浪が普通なのに半年で、というのがただものではないです。アートの作品も発表されていたとのことで、通訳時にアーティストの感覚的な表現をすぐに伝えられるのも納得です。
「卒業してからは、しばらく演劇祭の仕事に関わり、パフォーミングアートについても学びました。そのときに、言葉への興味もあるし翻訳と通訳を軸に仕事をしていこうと決心がつきました」
コロナ禍では一時オンラインの仕事が増えましたが、今は円安とはいえ、少しずつ現場での仕事が戻ってきているそうです。
「オンラインでは、ボディランゲージとかないから、お話される人との関係を築くのが難しい。通訳は、どれだけ信頼して自分の声だと思ってもらえるかが重要です。話している人と通訳者の信頼関係が感じられないとお客さんは心配になる。あとは、アーティストの通訳で日本のオーディエンスに向けて話すとき、文脈を足さないと伝わらない場合は補足したりします。専門用語や美術史を知らない観客にもわかりやすいように。でも、私が語りすぎないことも大事だと思っているので、どこまで踏み込むか気をつけています」
そのあたりのバランス感覚も持たれている印象でした。創作の現場では、一番情報を持っている通訳の存在が大きくなりすぎてしまうこともあるそうで、その部分も気を使っているとのこと。
「全体を俯瞰で見ていて、私が一番情報量を持っていると、私がコントロールできる権力になっちゃう。声のトーンで現場の空気も変わってしまいます。でも、笑顔で話していればいいわけじゃなくて、現場がピリついているときは、シリアスな雰囲気で訳すようにしています。私が変に平和主義を出してしまうと、起こるべきぶつかり合いや議論も起きなかったりしますので……」
アートの現場に漂う緊張感が伝わるエピソードです。この仕事の醍醐味は、尊敬しているアーティストに一番近い場所で、アイディアや発想に触れられることだと田村さんはおっしゃいます。
「アーティストの言葉の通訳をしてると、自分では考えつかないアイディアや世界の見方を、まるで自分が考えたみたいに言うことができます。他の人のおもしろい思考を自分の体を通して話す感覚が気持ちいいんです。その人の思考を自分の中に入れる感じ。どんなに親しくなってもそういう感覚ってなかなかないじゃないですか。俳優の演技と似ているかもしれません」
例えVIPでもダークな人の思考回路は自分に取り込みたくないですが、世界的に活躍しているアーティストなら、意識も高いしクリエイティブで、自分の脳にもいい効果を及ぼしそうです。
「大物アーティストはみんなめちゃめちゃいい人です」とのことなので、通訳するとエネルギーを吸収して人格もどんとん高まる効果が……?
美術鑑賞や創作活動だけじゃない新しいアート体験を提示してくださった田村さん。また美術展などで活躍しているお姿を拝見させていただきます。